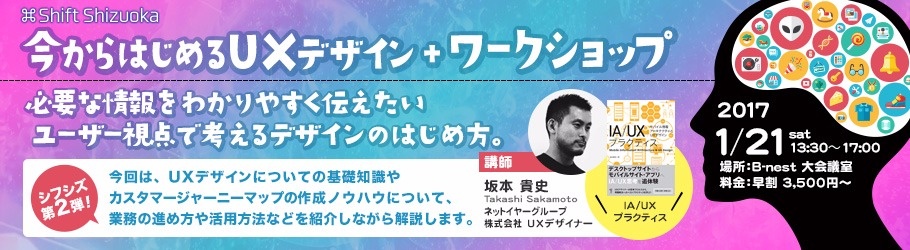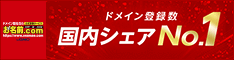| 雑感
Shopifyは予想以上にお金がかかるかもという話
Shopify、使ってますか? メディアでは「黒船」扱いされたり、Amazonと比較されたりと話題のASP型ECプラットフォームです。本体は、ベーシックプランで 月額33ドルから利用できます。国産の他社サービスと比べてもお高い感じはしないのですが、意外とお金がかかることがわかりました。
要因1)為替相場に左右される
Shopify はカナダの企業が提供するサービスで、利用料はドルで設定されています。2023年12月10日時点のドル円相場は 1ドル=145円ほどですが、年始には1ドル=130円ほどだったことを考えると、日本円換算では 10%ほどの「値上げ状態」と言えます。利用料金自体も2023年4月に価格改定(値上げ)を実施しています。
つまるところ、世界的なインフレと円安で利用料金自体が当初の想定よりも高く感じられてしまうわけです。
要因2)プラグイン(Shopifyアプリ)による機能拡張がほぼ必須
Shopify には Shopifyアプリという機能拡張システムが用意されています。ここにもお金がかかります。と言いますのも、Shopify はECサイトの基本機能(商品掲載・買い物かご・決済 etc)は提供されますが、送り状(配送会社の伝票)発行などは Shopifyアプリで賄うのが基本です。カナダの会社が世界規模で提供するサービスなので、国ごとのローカルな仕様は現地のデベロッパーが Shopifyアプリで提供するというわけです。
送り状発行アプリ、配送日・配送時間指定アプリ、熨斗などギフト対応アプリ、データエクスポートアプリなどなど、複数のアプリが必要なことも多いです。そして、それぞれが月額10ドルなどの利用料(こちらも基本はドルベース...)が発生するので、むしろShopify本体以上の費用になったりもします。
要因3)決済ページを改修するには Shopify Plus プランが必須
決済画面(配送先や決済手段を選ぶページ)で「こちらの商品もおすすめですよ」とか「あと◯円のお買い上げで送料無料」とか出したいこともあると思います。このページを変更するには Shopify Plus というプラン(?)に契約が必要です。こちら、参考価格 2,000ドル/月 となっております。月額約30万円ですので、おいそれとは提案できません。どうでしょう、月商1,000万円くらいが目安でしょうか(適当ですよ)。
そうは言っても、魅力的なプラットフォーム
お金の面で想定以上の支出が発生しうる Shopify ではありますが、「黒船」と言われるだけのことはあるのも確かです。ベーシックプランから多言語対応・越境ECが可能ですし(弊社ではサポート外ですが)、玉石混交ながらShopifyアプリの充実ぶり(少なくとも数だけは豊富)もあります。スタンダードプラン以上で使える Shopify Flow(オートメーションワークフローを組む機能)なんて、考えるだけで楽しいです。
そんなわけで、意外と安くない Shopify です(弊社のクライアントで、純粋なシステム利用料が25,000円/月ほど)。用法・用量を守って、適切にお使いいただくとよろしいかと思います。